 3840 PV
3840 PV
【BtoB受発注業務】企業間取引を効率化する受発注システムを...
2024.12.06
受発注システム 2404 PV
2404 PV
【受発注業務を効率化】業務内容を徹底解説!受発注システム導入...
2024.12.20
受発注業務 1536 PV
1536 PV
受発注システムと基幹システムの連携で進める業務効率化
2024.07.05
基幹システム弊社の受発注システム「MOS」をお客様に導入いただく際には従来のメリットである「業務効率化」、「負荷軽減」、「業種業態にあった機能やしくみ、カスタマイズ」をご案内させていただくと同時に普段では気づくことができない“無駄”を潰すことができる点も説明しております。
今回はそんな“気づかない無駄”についてご紹介いたします。
目次

多くの会社が「FAX・電話・メールで発注、相手が確認して返信」という流れを使っていますが、この“非同期”が現場に以下のような見えないコストを発生させています。
FAX・電話・メールで発注してから返信が来るまでの時間がどれくらいなのかが分かりません。相手が内容を誤解していた場合、再確認・訂正が発生してしまいます。
営業終了後や休日にFAXやメールで発注をしても、相手からは翌営業日の確認・返信となってしまいます。現場では「返信はまだか」、「発注は大丈夫か」と確認のフローが発生してしまいます。
取引先によって発注受付、確認のレスポンス速度に差があるため、どの取引先にいつ催促すればよいかの判断が難しくなってしまいます。
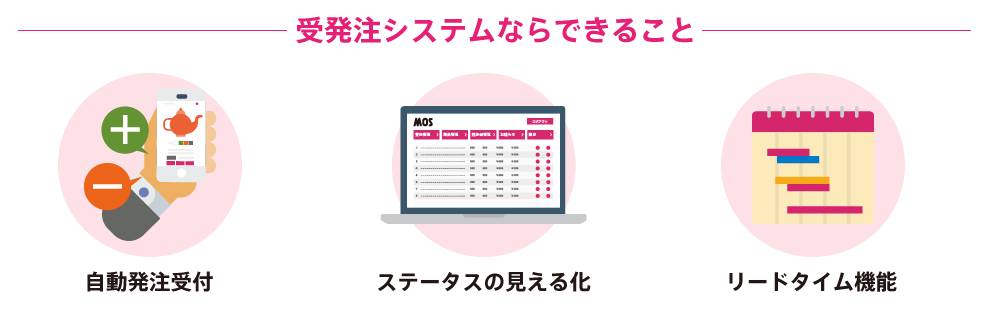
受発注システムの場合、「発注受付の自動確認」や「発注ステータスの見える化」、「締め切り時間・リードタイム機能」等を備えており、この“非同期遅延”をデータや数値で把握、短縮できるしくみを提供しています。

受発注の現場では発注書のフォーマットが統一されていなかったり、仕様があいまいだったりすることが、意外と工数を食う原因になっています。
発注仕様が曖昧な事で部品や納品形態の誤解を生み、現場が納品を受けられない状態になってしまい再発注を余儀なくされてしまう。
発注数量の端数処理・単位の違い(箱、kg、パックなど)で「どの基準で発注するか」が担当者によって異なってしまい、定期的な修正依頼が発生しトラブルに。
包装・梱包形態、ラベル表記など取引先間でのルールが揃っていないため、納品先で返品・手戻りが発生してしまう。
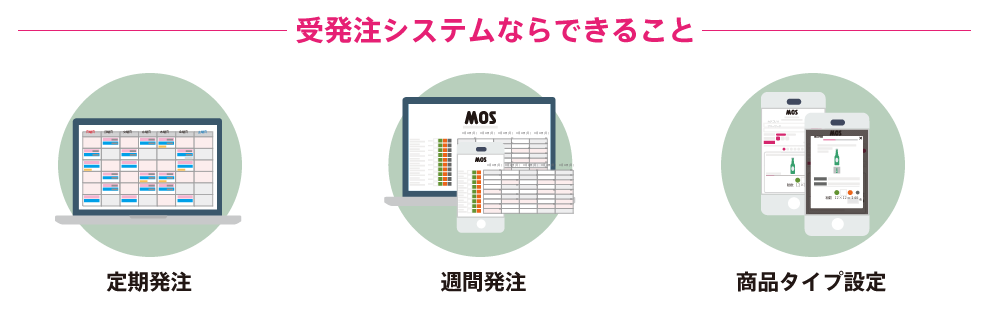
受発注システムには定期発注や再発注、週間発注などの機能を持つものがあり、発注先ごと・商品タイプごとに発注仕様を設定することができます。さらに発注時には前回との内容の差異、仕様差異を自動検知・警告する設定が可能です。これにより手戻りを減らしてスムーズな納品を実現します。

在庫保管コストや機会損失(欠品リスクなど)は、発注そのものより「いつ発注するか」に強く影響を受けます。
季節変動・販促イベントなどのタイミングを考慮せず定期的に発注をしてしまうことで、販促前に余剰在庫を抱えてしまい廃棄や割引処分が必要になることも珍しくありません。
さらに、取引先の納期リードタイムの変動を把握していないと入荷遅延で販売機会を逃してしまいます。
トラブルを防ごうと発注回数を減らそうとして大量発注してしまうと、保管スペース不足や資金繰りの圧迫が発生してしまいます。

受発注システムでは取引先ごとの過去納期データを可視化でき、「発注タイミング通知機能」などの機能を搭載しているものもあります。これにより、余裕在庫でも不足でもない、最適な発注タイミングを予測できるようになります。

受発注業務には「ちょっと判断が必要な場面」が多数あります。これら小さな意思決定が毎日何十回も起こることで、現場の負荷が目に見えない形で増えていきます。
発注数量の微調整(過去実績を参照すべきか、安全在庫を考慮すべきか)
発注先変更(価格が安ければ別先、納期重視なら従来の先)
緊急発注の優先順位付け
これらの判断標準が曖昧だと、担当者がその都度過去データを探したり上司に確認する必要が発生し時間を消費してしまいます。

受発注システムなら「締切時間までの発注内容の変更」、「発注者・取引先の割当機能」、「承認フロー機能」といった機能があり、判断に迷う場面を大幅に減らすことができます。

受発注業務の効率化は、大量取引先・定型発注を中心に取り上げられることが多いのですが、小規模の取引先や非定型発注先(注文が不定期・仕様が変わる先)とのやり取りにこそ“見落とされがちな無駄”があります。
非定型商品・包装の仕様・納期交渉などの複数やり取りの際に、同じ社内で伝言錯誤が起こってしまい、結果的に取引先に迷惑をかけてしまう。
過去の発注内容が属人的・紙ベースで残っていたため、再発注内容の確認に時間がかかり、発注に時間がかかってしまったり、発注内容にミスが起きてしまう。
取引先ごとに発注までの手順が異なり、担当者が毎回内容を確認する必要がある。そのため対応が遅れ無駄が発生してしまう。

受発注システムなら、こうした小規模かつ非定型の取引先にも対応するため「商品の割り当て」、「取引先別荷姿設定」、「取引先選択機能」などを搭載しています。こうした機能により、定型外発注の処理時間・迷いが削減され、対応品質も安定させることができます。

これらの“他ではあまり注目されない受発注業務の無駄”を潰すことで、現場の負担が思った以上に減ることがあります。もし、「我が社でもこんな無駄があるかもしれない」と思われたら、ぜひ受発注システムを使った現状分析・改善プランを一緒に考えてみませんか?
MOSは、単なる受発注システムではなく、企業の業務改善、課題解決のパートナーです。
既に受発注システムを利用していただいているユーザー様も、これからの利用を検討されているユーザー様もぜひ一度「MOS」に触れてみてください。他社との違いや使いやすさ、シンプルさをきっと実感いただけるはずです。
さらに詳しく知りたい方はぜひ「MOS」のご紹介ページをご覧ください。